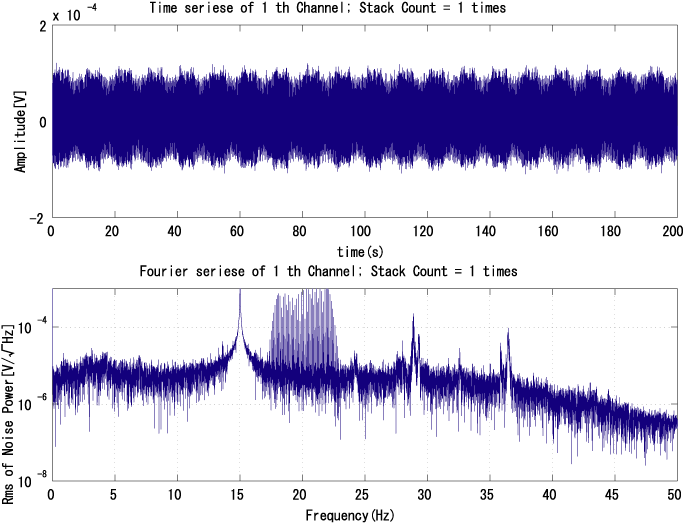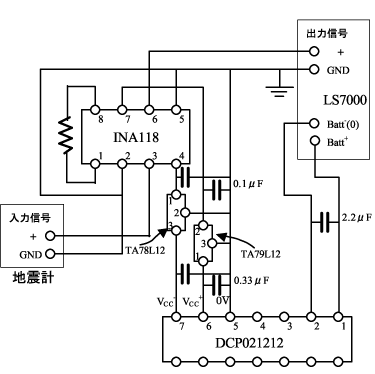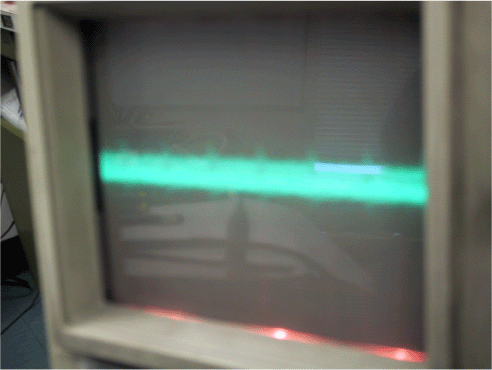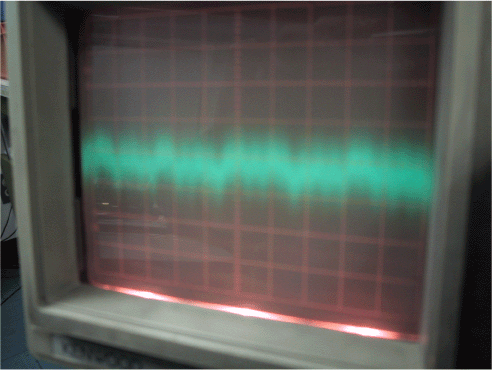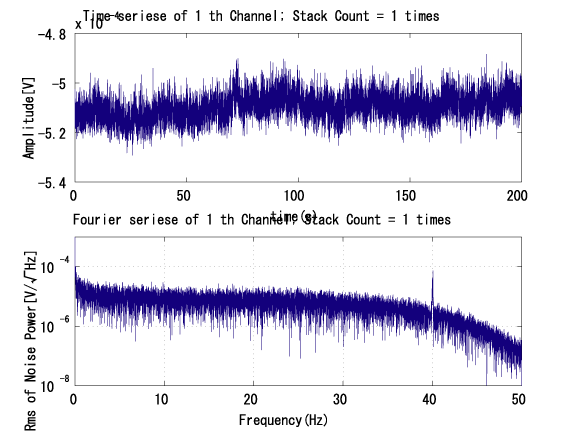LS7000のためのアンプ作成
2003年淡路島ACROSSアレイ観測のため,LS7000用にINA118(Bur Brown)を用いてアンプを作成したので覚え書きついでに報告する.
 LS7000の仕様と観測計画
LS7000の仕様と観測計画
LS7000は24bitΔΣ型のADを用いた地震観測用のデータロガーで,その主な仕様は白山工業HP 参照.ダイナミックレンジは17bit = 約105dB.ただし入力レンジは±1Vと±10Vしか選べず,その際の入力分解能はそれぞれ約16μV,160μVである.入力レンジ±1Vで入力をショートさせた記録が図1である.

図1.入力レンジ1Vの際の入力ショート波形.
a) 時間波形,オフセットはほとんど無いが,ドリフトが見える.b) 周波数波形.単位時間,単位周波数あたりのノイズパワーの平方根.10〜30Hzでは約1e-5V/√Hz
我々が2003年淡路島ACROSSアレイ観測で用いる地震計(Mark Product 4.5Hz)の感度は約0.3V/kineでありその際,入力レンジ±1Vの際の分解能でもせいぜい約± 50 μkineつまり5e-7m/sである.地動ノイズは淡路島ではこれを多少下回るようである.
図2は淡路島において実際にMark Product 4.5Hzで取得した波形である.図1と比べて,10〜30Hzではほとんどかわりがないように見える.
15Hz付近から広く裾野を引いたスペクトルは,低周波ユニットをGPSに同期させずに15Hzで運転した信号.また,17〜23Hzのラインスペクトルは,高周波機を19±2.5HzのFMで運転した信号である.
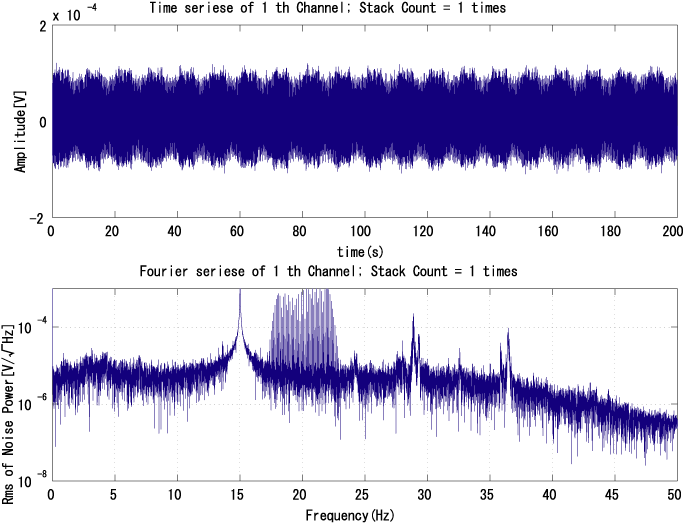
図2.入力レンジ1Vの際の淡路島での観測波形.出力はV表示.a) 時間波形,オフセットはほとんど無いが,やはりドリフトが見える.b) 周波数波形.単位時間,単位周波数あたりのノイズパワーの平方根.10〜30Hzでは約1e-5V/√Hz
というわけで,淡路島ACROSSのS-N比を上げるために,このロガーの前にプリアンプを入れてやる必要がある.
 アンプ製作
アンプ製作
さて,用いるICはBurr-Brown社製,INA118PB.これは低オフセット電圧(50μVmax),低温度ドリフト(0.5μV/℃),高CMR(110dB)で,低消費電流(350μA)が売りのインスツルメンテーションアンプ.RSで入手した.さてこの際問題は電源である.±2V以上の両電圧が必要.結論を先に言うと電源は電池からとるのが最適?ということになるが,今後の参考のためにDC-DCコンバータについても述べよう.
電源 = LS7000バッテリ端子
LS7000のコネクターからは,+12Vの片電源が出ている.これを用いて±5V以上の安定した両電圧を得ることを試みた.用いたのはBurr-Brown社製のDC-DCコンバータDCP021212P.これは89%電圧保証で,+12Vから±12Vを作ってくれるDC-DCコンバータであるが,多少難があり,負荷が無い状態で,なんと±24Vが出てしまうというものだった.また,TIのカスタマーサポートによると,個々の特性がそろっていないことがあるそうで,「量産にはあまりお勧めできない」とのこと.しかし代替品はないそうで,10セットならば一つずつ特性を確かめれば良いだろうということで回路を組んでみた.
このDC-DCコンバータがどれほどのノイズを発生するのか,またそれが信号にどれだけ影響するのかを評価する.
図3は回路図である.
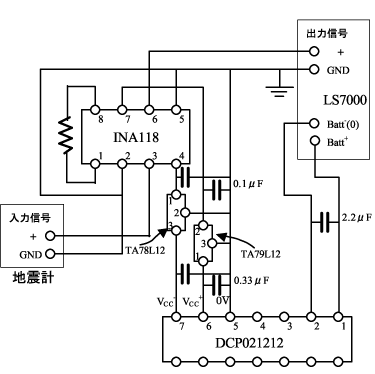
図3.回路図.INA118は基本的に差動入力だが,地震計の出力端子は差動ではないため,マイナス端子を出力,電源のグランドと共通とした.
この時DCP021212を通さず電源電圧を測ったものが図4である.またこれをDCP021212に通したものが図5,またこの時入力信号をショートした信号出力波形は図6となる.
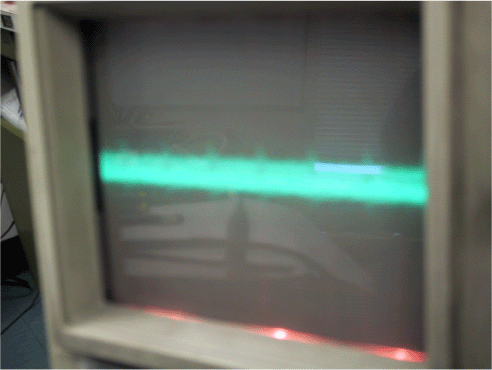
図4.LS7000のバッテリー端子からの電源電圧.ボーっと光っている部分の幅は約0.1V.ひげは約13μs(80kHz?).

図5.LS7000のバッテリー端子を電源とした時,DCP021212を通し,3端子レギュレータに通して±12Vにして整流した電圧.DCP021212を通した時点での電位差は±15V(12VになっていないのはDCP021212せいと思われる),縦軸は20mV.ひげは約13μs(800kHz?=DCP02のスイッチング周波数)で±20mV.

図6.LS7000のバッテリー端子を電源とした時の出力信号波形.電源のノイズが信号に乗っているのが判る.縦軸は1目盛りが0.1Vある.横軸は1目盛り1μ秒
電源 = 乾電池
次に電池を電源にした際に,電池からの電源出力(±4.5V)の揺らぎとその際の信号のオシロスコープによる記録を見る.
図7,図8である.これを見ると一目瞭然,電池の方が低ノイズの優れた電源であることがわかる.

図7.電池からの電源電圧.ひげの部分は±1mVある.横軸1目盛りは10μs
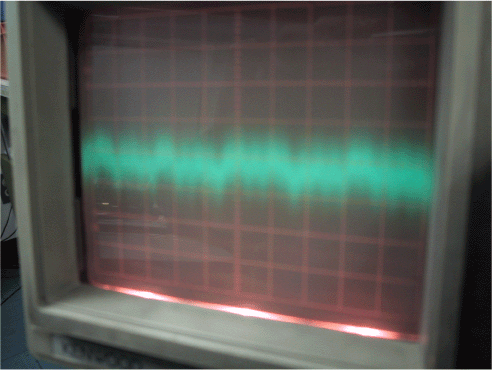
図8.電池を電源とした時の出力信号波形.3端子レギュレータは通している.電源のノイズはほとんど無く,信号に乗っている揺らぎが何かは判断できない.縦軸は1目盛りが1mV.横軸は1目盛り1μs.
 出力波形
出力波形
上のLS7000のバッテリ端子と電池それぞれを電源にした際のLS7000の出力波形を示す.
ΔΣ-AD変換をした記録としては,図9のような波形になる.0Vオフセットの大きさ約1mVは,時によって変わるが,数mVより大きくなることは無い.出力をオシロスコープで見た際にはひげが最大0.1V程度あったのに,数mVに抑えられているのは出力波形にローパスフィルタをかけているためと考えられる.また,電池を使用した際にもほぼ同様の波形が得られ,ノイズレベルは違わないように見えるが,電池の時は60Hzが乗っている.これは電池のほうで商用電源を拾っているようだ.

図9.ls7000のバッテリ端子からDCP021212を電源とした時の出力信号波形.
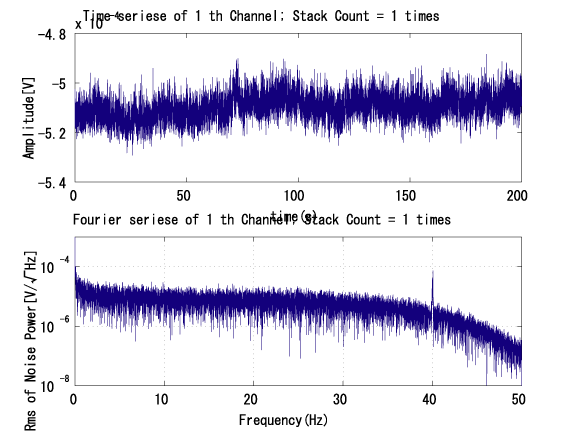
図10.電池を電源とした時の出力信号波形.3端子レギュレータは通していない.電池は3個ずつ直列にし,±4.5Vを電源とした.ただし,電池の中点はGNDに落とした.
Awaji実験のトップへ
実験のトップへ