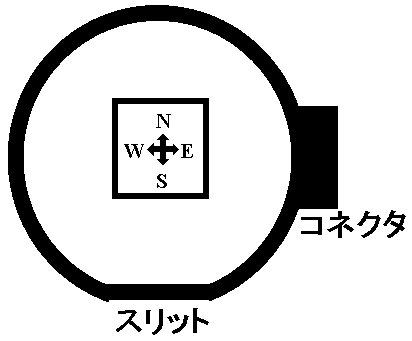 全ての地震計の成分がこうなっている様だが、なるべく確認してから使う事にしよう。
全ての地震計の成分がこうなっている様だが、なるべく確認してから使う事にしよう。| 1 | NS+ (青) | 2 | NS- (緑) | 3 | EW+ (白) | 4 | EW- (ピンク) | 5 | UD+ (赤) | 6 | UD- (黄) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | NS CAL+ | 8 | NS CAL- | 9 | EW CAL+ | 10 | EW CAL- | 11 | UD CAL+ | 12 | UD CAL- |
| 13 | +V (?意味不明) | 14 | -V (?意味不明) | 15 | COM | 16 | F.G. |
| 会社 | RION | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | AC 6V 又は 単 3電池 4個 (アルカリ形で連続約 20時間測定可能) | |||||||||
| 感度 |
|
| 会社 | MARKRAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | 無し | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感度 | 100 V/(M/S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方位 | 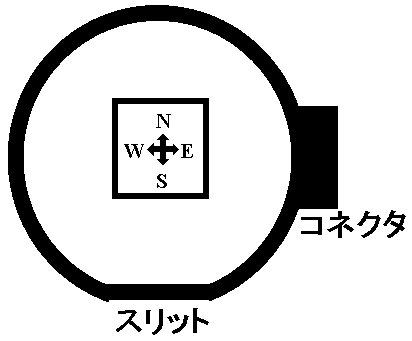 全ての地震計の成分がこうなっている様だが、なるべく確認してから使う事にしよう。 全ての地震計の成分がこうなっている様だが、なるべく確認してから使う事にしよう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| センサー出力信号対応表 | カッコ内の色は 4.5Hz が入荷された頃に作った時のケーブルの色である。今後作る時もなるべくこの色に対応するように作る様にしよう。
|
| 会社 | RION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費電流 | +5 mA 以下、-3 mA 以下 (DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感度・分解能 | 0.3 V/(M/S)^2 ± 1% (DC) 及び 3×10^-5m/s^2 以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定周波数範囲 | DC 〜 100Hz (±10%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大測定加速度 | ±25 m/s^2 (約2.5G) (10Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感度温度係数 | 約 +0.04 %/℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感度電源電圧係数 | ±0.001 %/V 以内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノイズ | 2.1 μm/s^2/sqrt(Hz) 以下 (周波数 0.1〜10Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横感度比 | 1 %以下 (DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケースアライメント | 0.5 度以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零点不平衡 | 0.3 m/s^2 以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| センサー出力信号対応表 | LS10C のセンサーからの出力
LS-13A からの出力
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LF-10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LF-20 | LF-10 が 1台のみの接続に対し、LF-20 は 3台接続させる事ができる。 |
Serial Number による違い
| Serial Number | 52860797 | 52860803 |
|---|---|---|
| 電圧感度 | 0.299 V/ms^2 | 0.299 V/ms^2 |
| 横感度比 | 0.05 % | 0.17 % |
| 零点不平衡 | 0.01 m/s^2 | 0.02 m/s^2 |
| 測定温度 | 25 度 | 25 度 |
| 測定年月 | 1996/9 | 1996/9 |
| 会社 | lennartz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | 12V (9〜15V) DC , approx.100mW (つまり消費電流約 8.3mA) | ||||||||||||||||||||
| 感度 | 400 V/(m/s) | ||||||||||||||||||||
| 固有振動数・減衰定数 | 1Hz 及び 0.707 | ||||||||||||||||||||
| 測定上限周波数 | 80Hz | ||||||||||||||||||||
| センサー出力信号対応表 |
|
| 会社 | AKASHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | DC15V ± 10% , 18mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感度・分解能 | 0.306 V/(m/s^2) ± 10% 以内 [3V/G に相当] (全成分同じ感度) 及び 5×10^-6G (DC) V403 とはセンサー名の事である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固有振動数・減衰定数 | 490Hz 及び 0.6〜0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定周波数範囲 | DC 〜 400Hz (±5% 標準値) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定範囲 | ±3G (水平方向) ・ ±2G (垂直方向) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直線性 | 0.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1G における温度による感度変動 | 0.02 %/℃ (MAX.)/TD> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横方向感度 | 0.001 G/G [約0.1%という事か?] (MAX.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケース軸・感度軸のずれ | 0.5 度 (MAX.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零点不平衡 | 0.02 G (MAX.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度による零点不平衡 | 0.001 G/℃ (MAX.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力抵抗 | 2.8 KΩ (標準値) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| センサー出力信号対応表 | カッコ内はマニュアルに書いてある物だが、実際は違っているようだ。
|
| 会社 | AKASHI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | DC 24V ± 10% 30mA だが消費電流は個別のセンサーの試験成績書には、以下の様に書いてある。
| ||||||
| 感度・分解能 | 0.510204 V/(m/s^2) [5V/(9.8m/s^2)] (全成分同じ感度) 及び 49×10^-6 m/s^2 (DC) | ||||||
| 固有振動数 | 450Hz (90度位相ずれ)。だが個別のセンサーの試験成績書には、以下の様に書いてある。
| ||||||
| 減衰定数 | 0.6 〜 0.7 | ||||||
| 測定周波数範囲 | DC 〜 400Hz (±5% 標準値) | ||||||
| 測定範囲 | 9.8 m/s^2 (約 1G) だが個別のセンサーの試験成績書には、全てに ±33.3m/s^2 と書いてある。 | ||||||
| 直線性 | 0.05 % | ||||||
| 1G における温度による感度変動 | 0.02 %/℃ (MAX.) | ||||||
| 出力抵抗 | 5 KΩ (標準値)。だが個別のセンサーの試験成績書には、以下の様に書いてある。
| ||||||
| 横方向感度 | 0.0098 m/s^2/(m/s^2) [約 1% という事か?] (MAX.) | ||||||
| ケース軸・感度軸のずれ | 0.5 度 (MAX.) | ||||||
| 零点不平衡 | 0.196 m/s^2 (MAX.) | ||||||
| 温度による零点不平衡 | 0.0098 m/s^2/℃ (MAX.) | ||||||
| センサー出力信号対応表 | 手元に資料無し。 |
| 会社 | GURALP |
|---|---|
| 電源 | AC 100V (CONTROL BOX を使用) |
| 感度 | 1500 V/(m/s) [360 Sec Velocity Sensor] |
| 方位 | 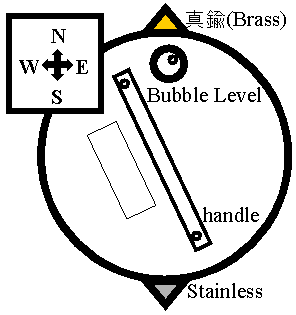 |
| 会社 | MARKRAND | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | 無し | ||||||||||||||||||||||||
| 感度 | S.N. : 9410007において、
| ||||||||||||||||||||||||
| 方位 | 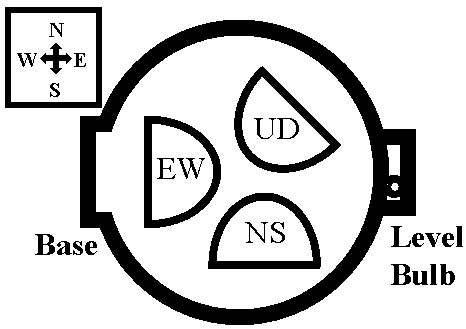 | ||||||||||||||||||||||||
| センサー出力信号対応表 | カッコ内の色は標準で付いているコネクタケーブルの色である。
|
| Rs | a1 | D1 | D0 | R0 |
|---|---|---|---|---|
| シャント抵抗 (KΩ) | 30 (定数) | 設定したい減衰定数 (普通 h=0.7) | 0.01 (定数) | コイル抵抗 (KΩ) |
| - | 上記の計算式から導出した値 | 山岡先生談の値 | 山岡先生談の値に1MΩのロガーを接続したと想定した時 |
|---|---|---|---|
| 上下動 | 38.78 KΩ コイル抵抗: 4.7KΩ を使用。 但しこれは古いタイプの上下動の値 | 24.2KΩ (平均値) | 24.8KΩ (平均値) |
| 水平動 | 38.78KΩ コイル抵抗: 4.7KΩ を使用。 | 43.275KΩ (平均値) | 45.23KΩ (平均値) |
| e0 | RS | R0 | Gc |
|---|---|---|---|
| 出力電圧 (V) | シャント抵抗 (KΩ) | コイル抵抗 (KΩ) | キャリブレーション定数 (g*cm/s^2 ?) |
| G0 | m | f | I |
| 感度 (V/kine) | 振り子の重量 (約 0.2 kg) | 入力信号の周波数 (Hz) | キャリブレーションコイルへの入力電流 (A) |
| 会社 | RION |
|---|---|
| 電源 | AC100V±10% , 50/60Hz , 約10VA |
| 感度 | 0.05 , 0.1 , 0.2 V/Gal の 3段階 |
| 固有振動数 | 約 800Hz (0.1 V/Gal) |
| 測定周波数範囲 | 0.1 〜 100Hz (±1dB 固定時) 低域カットオフ周波数 0.03Hz (-3dB) |
| 増幅率 | ×1 , ×10 , ×100 の3段 |
| 感度温度係数 | + 0.2 %/℃ |
| ノイズ | 1 μV/sqrt(Hz) (周波数 1Hz , 感度切替 0.1 V/Gal , 増幅率切替 ×1 の時) |
| 横感度比 | 1 %以下 (振動数 5Hz 時) |
| 会社 | 東京測振 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | DC ±15V (±5 %) | ||||||||||||||||||||||||
| 感度 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 方位 | 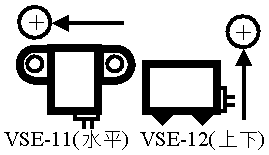 | ||||||||||||||||||||||||
| 精度/分解能 | 基準感度誤差 ±0.5 %以下 / 10^-5 m/s (1mkine) 以下 | ||||||||||||||||||||||||
| 振り子固有周波数 | 1.5 Hz | ||||||||||||||||||||||||
| 制動定数 | h = 約 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 測定周波数範囲 | 0.025 〜 70 Hz | ||||||||||||||||||||||||
| 直線性/横感度 | 0.05 %以下 / 0.3 %以内 (10Hz,1000galにおいて) | ||||||||||||||||||||||||
| 検定コイル | 約 15 μA/gal | ||||||||||||||||||||||||
| センサー出力信号対応表 |
|